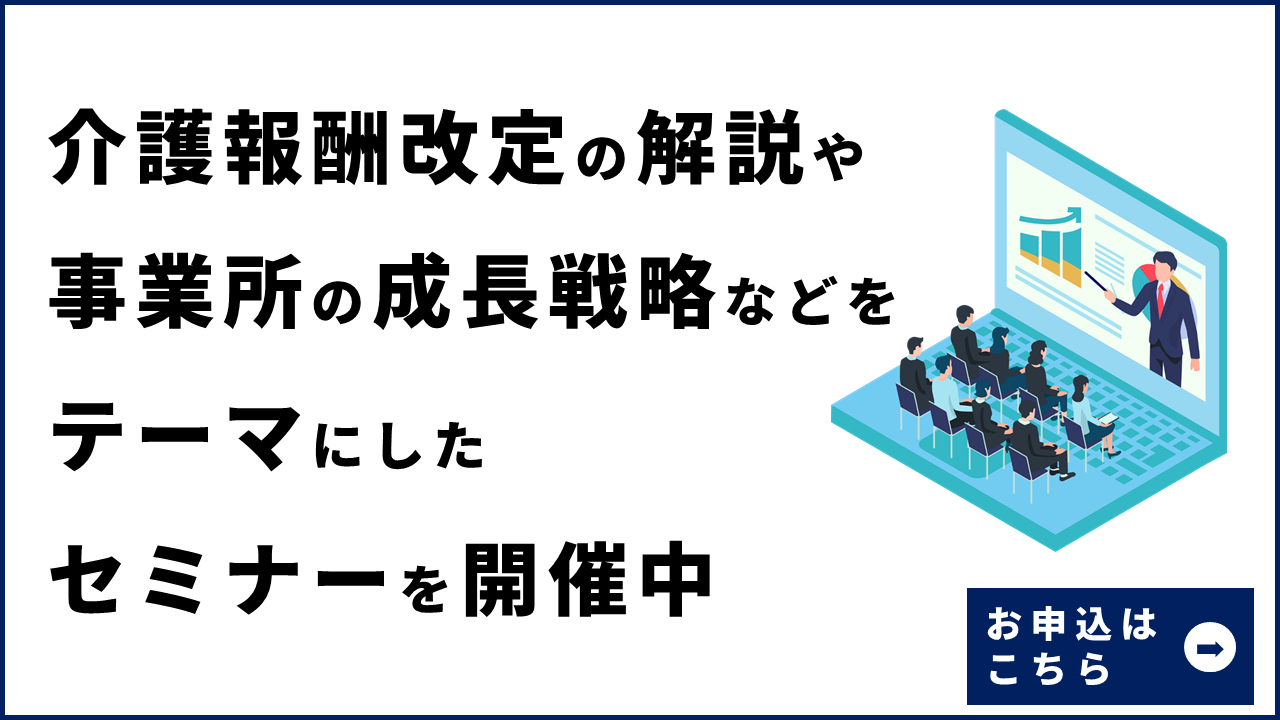- 介護/福祉
- #施設経営
自立支援に即した介護サービスの基本と事例①
2021.11.10

【目次】
1.介護事業における自立支援の考え方
平成24年の介護報酬改定で「自立支援型サービスの強化と重点化」が示されて以降、介護事業において『自立支援』は当たり前に周知されるようになりました。介護に携わるスタッフも、「利用者の身体や、生活を改善したい」と常々考えているのではないでしょうか。しかしながら、経営的にも介護度が高い方が高報酬に設定されているため、身体機能や生活機能、要介護度を改善することに対して、積極的になれるインセンティブが働きづらいという状況が一面ではありました。もちろん、改善に向けて日々努力している事業者は非常に多いけれど、報酬という形では報われることはありませんでした。
平成30年の介護報酬改定では「自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現」が示され、『自立支援』と『重度化防止』がより強く結びつけられ、これまでの介護保険の歴史の中で初めて身体機能の維持・改善の実績が加算という形で評価されることなりました。同じころ、品川区や川崎市など、維持・改善に積極的な自治体を中心に、改善時のインセンティブが設定され、目指すべき方向性の1つとして着実に広まっていったと考えています。
具体的な内容としては、平成24年の介護報酬改定では、通所介護(デイサービス)の機能訓練への加算(個別機能訓練加算Ⅱ)が新設されました。通所介護(デイサービス)においても目的をはっきりさせた上で、機能の維持・改善に対する取り組みを推進していこうというものです。平成30年の介護報酬改定では、ADL維持等加算が新設、その後、令和3年の介護報酬改定では報酬もアップしました。他にも、周辺の加算として、栄養~加算など、複数の加算が新設されました。
この通所介護(デイサービス)の改定の流れは、利用日だけでなく、中長期的な目標を見据えて、利用していない日の支援、機能訓練だけでなく、栄養、薬剤等、生活全般を支援していこうという考え方がベースあるのではないかと考えられます。
しかし、介護保険ではマンツーマンでの機能訓練は前提とせずに、小集団での機能訓練で良いとされていること、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等のリハビリの専門職を機能訓練指導員とせずに、看護師等でも良いとされていることから、維持・改善に思うような成果がでていない事業所もあるのではないでしょうか。また、改善していると判断する為には測定の必要がありますが、オペレーション上の課題や、測定する目的が計画書に記載するためになっていることも多いのではないでしょうか。
上記の背景を踏まえて、本コラムでは、自立支援に則した介護事業を目指し、特に介護の質を可視化し、質の評価に向けた準備を行っていく基本的な考え方をご説明いたします。
2.『科学的介護』や『自立支援』に関する議論の大きな流れ
従来、介護保険サービスの評価は、ドナベディアン・モデルでいう、ストラクチャー評価にとどまっていました。「ストラクチャー」とは「構造」を意味し、つまり、サービス提供に関して設備・人員体制等を評価するということを示しています。この評価基準は、人員体制や提供環境などをある水準まで引き上げることを目的としています。基本報酬上の人員基準に上乗せした、介護福祉士や看護師、理学療法士・作業療法士の配置に対する評価がこれに当たります。
しかし、例えば介護福祉士数、看護師数、理学療法士・作業療法士数が一定程度の介護事業者が提供した介護サービスの質は必ずしも一定ではなく、当然利用者・入居者の属性やスタッフの質、サービス提供方法などによって異なります。同様に、“リハビリテーション”を例にとっても、私たちが経営コンサルタントとして、数多くの介護施設に関わらせて頂いた経験からも、“リハビリテーション専門職の体制”と施設で提供されている“リハビリテーションの質”は必ずしも相関しているとは感じないことが多いです。
リハビリテーション専門職の人数が少なくても、システムが整っていたり、環境が適切であったり、専門職以外のスタッフのリハビリマインドが高ければ、リハビリテーション専門職の人数以上の効果を生み出すことが出来ます。つまり、ドナベディアン・モデルの「プロセス評価」「アウトカム評価」を併用することが不可欠なのです。したがって、この法改正の流れは“自立支援”という観点からは、当然のものと考えられます。
また、これまでの法改正の流れや、近い領域である医療領域の診療報酬改定を見た際に、新設された加算は一定の目標を達成すると基本報酬に内包化される可能性があります。例えば通所介護(デイサービス)における送迎加算や施設系サービスにおける栄養マネジメント加算がその例です。医療においても、診療報酬改定によって平成29年から導入された回復期リハビリテーションにおける「アウトカム評価」である「実績指数」は、施設基準に包括化されました。施設基準におけるアウトカムの指標としては「在宅復帰率」「日常生活機能評価」「実績指数」の3つとなりました。もう少し説明すると、この施設基準は入院料に直結するため、医療機関としても結果が出ていなければ、同じだけのスタッフや提供体制をとっていても報酬に差が出てくることになります。
この様に、加算として設定されているテーマについては、時間の経過とともに当たり前のサービスになっていき、取り組みをおこなっていないことそのものがリスクになってしまう可能性もあります。算定が一見難しく見える加算に対しても不要だからと避けるのではなく、「どうしたら算定できるか」の視点を持って取り組むことが重要だと考えられるでしょう。
3.介護事業における「アウトカム評価」とは
介護事業で求められるものは、介護サービスそのものだけでなく接遇やコミュニケーションなど様々あります。法改正により、介護事業で求められる「アウトカム評価」は、特に「介入の結果」ということです。例えば、“通所介護(デイサービス)を利用することでADLの評価(Barthel Index)が向上した”であるなど、質を評価できる「アウトカム」を定義し、それをもって質を測る取り組みということになります。
近い領域の医療ではすでに古くから導入されています。在宅復帰率や入院期間、回復期リハビリテーション病棟で導入されている「実績指数」などがそれにあたります。「実績指数」は在院日数を分母、ADLの改善度合いを分子に置いたものであり、在院期間が短く、改善度が大きい場合に高く評価されるようになっています。
介護事業においても、同じサービスで同じような利用者層だとした場合で、一方の施設は利用者の能力を維持・改善できていて、一方の施設はそうでない場合、同様の報酬となってしまっては維持・改善しなくてもよいと捉えかねられないでしょう。また仮に高齢者を維持・改善できる手法がきちんと整えられれば、介護サービス自体の社会的な評価の向上にもつながってくると考えられます。
平成30年改定では、通所介護(デイサービス)には“ADL維持等加算”が新設されました。これは通所介護(デイサービス)に定められた初めてのアウトカム指標で、(Ⅰ)が3単位、(Ⅱ)が6単位と非常に単価設定は低いですが、令和3年改定では(Ⅰ)が30単位、(Ⅱ)が60単位と10倍になりました。法改正によって“アウトカム”を求めていく姿勢を示されたと捉えられます。この加算を算定する為には、定期的な測定やその分析が実施できる体制が必要になりました。
介護事業の通所介護(デイサービス)において初めて取り入れられた「アウトカム評価」は今後、その他のサービスにも広がっていくこととなります。