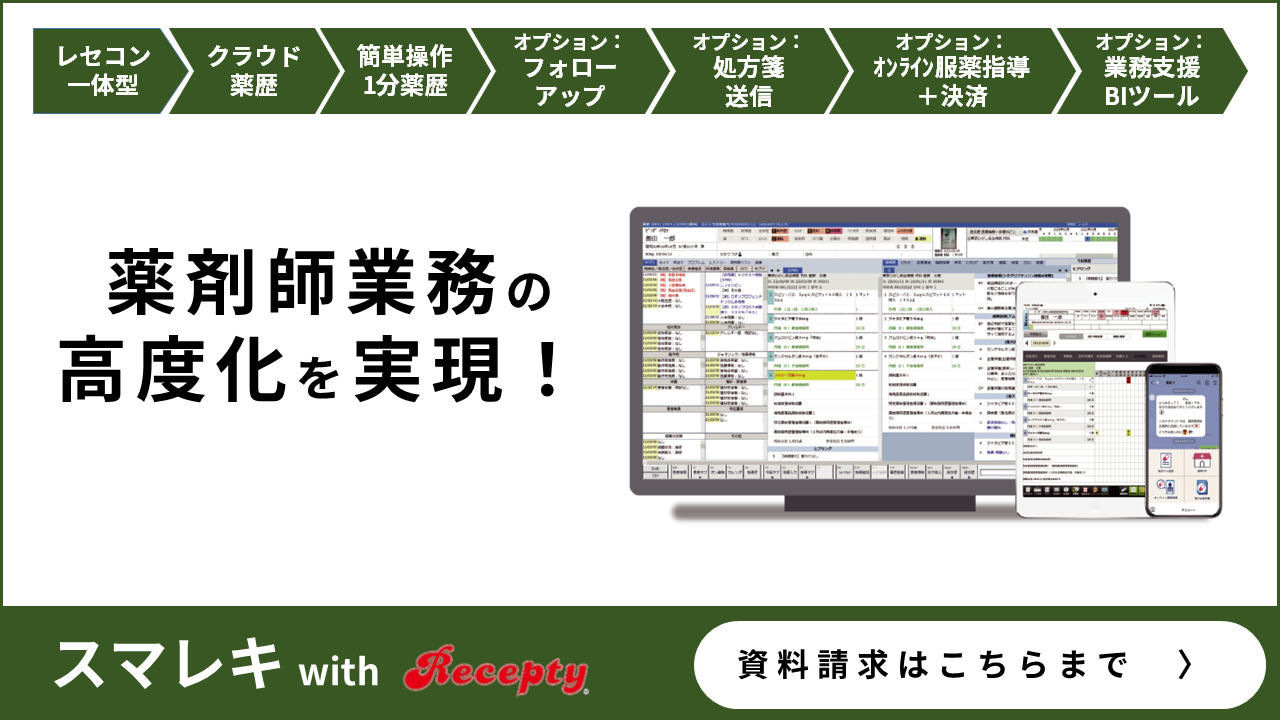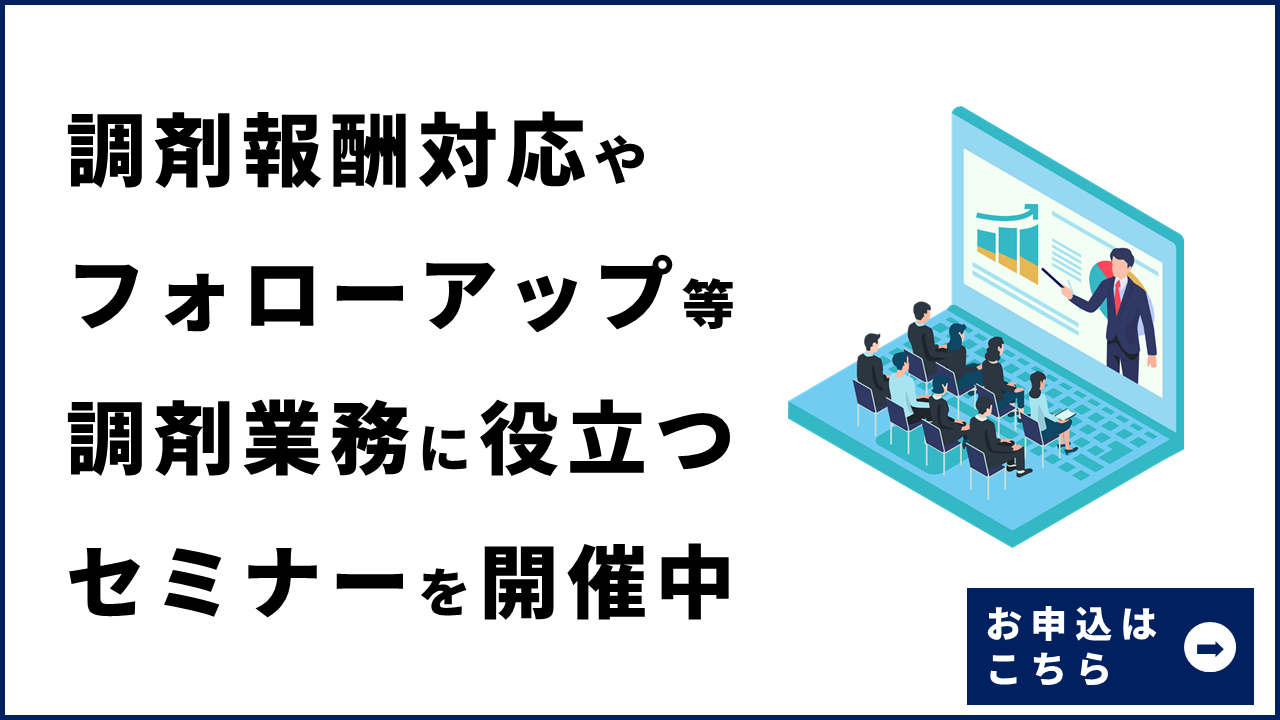- 調剤
- #薬局経営
セミナーレポート「薬局薬剤師による抗菌薬マネジメントのキホン ~蜂窩織炎を中心に~」
2024.03.27
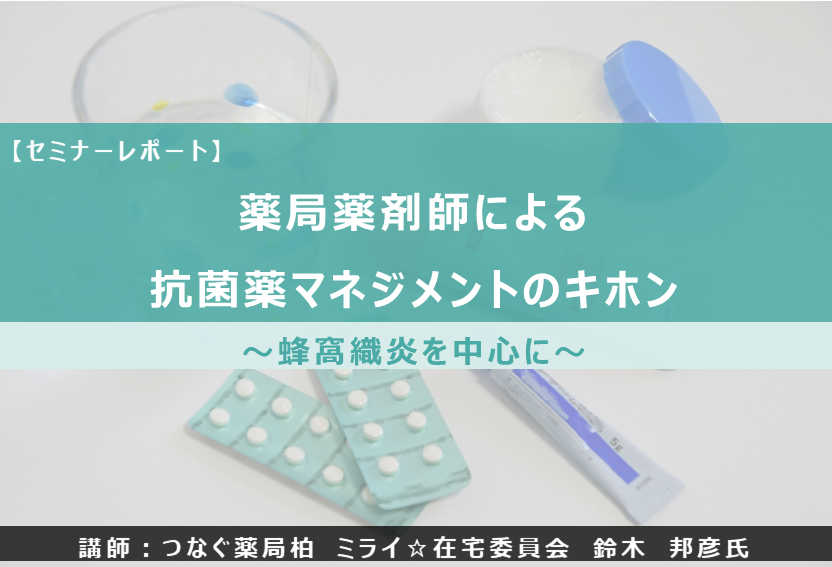
2月27日に一般社団法人ファルマ・プラス主催によるオンラインセミナー「薬局薬剤師による抗菌薬マネジメントのキホン~蜂窩織炎を中心に~」が開催された。講師の鈴木邦彦氏は本セミナーのゴールを、抗菌薬への苦手意識を減らし、感染症治療における薬歴の記載方法を学び、薬剤師としてスキルを高めることとして、薬局業務ですぐに役立つ内容を解説した。ここではセミナーの一部を紹介する。
【セミナー講師と演題】
演題:薬局薬剤師による抗菌薬マネジメントのキホン ~蜂窩織炎を中心に~
講師:つなぐ薬局柏 ミライ☆在宅委員会 鈴木 邦彦氏
【目次】
1.抗菌薬を学ぶ際のポイント
抗菌薬を学ぶ際に重要なのは順番であり、「感染症⇒細菌⇒抗菌薬」の順に学ぶことをすすめたい。どの感染症から学び始めるかを迷う場合は肺炎・尿路感染症・蜂窩織炎から、細菌で迷ったらβラクタム系(経口セフェム)から始めることを推奨する。また、添付文書や製薬会社の製剤説明は、効力の大小すべて含めて適応菌種とされており、実用的ではないため勉強には適さないので、書籍で学ぶことをすすめたい。
感染症治療では、感染臓器(感染症)・感染微生物(細菌)・抗菌薬の3点を紐づけして理解を深め、その3点に個々の患者背景や重症度を組み合わせて考えることがポイントだ。
2.蜂窩織炎の例
上記の3点に蜂窩織炎を当てはめると、感染臓器は真皮~皮下組織、感染微生物はA郡β溶連菌・黄色ブドウ球菌、抗菌薬がセファレキシン・セファクロルとなる。
皮膚の感染症である蜂窩織炎を理解するためには、始めに皮膚の構造を学ぶ必要がある。皮膚は表面から、表皮⇒真皮⇒皮下組織⇒筋肉とミルフィーユ状に積み重なっており、表面に症状があるほど軽く、深くいくほど重症。真皮~皮下組織に感染している蜂窩織炎は皮膚の感染症の中では重めであり、筋肉までいく壊死性筋膜炎という病気は救急搬送レベルである。
また、蜂窩織炎は発赤・圧痛・発熱の3症状がみられるのが特徴で、顕微鏡で見ると蜂の巣に似ているため蜂窩織炎と名前がついたとされている。手足での発症が多く、四肢、顔首と続き、体幹は少ないのも特徴である。すり傷や切り傷、虫刺され部位、水痘、動物に噛まれたところ、他の発疹などから細菌が侵入して発症し、足白癬、アトピー性皮膚炎、リンパ浮腫などがあると感染リスクが高まる。
3.感染微生物と抗菌薬について
蜂窩織炎を含む皮膚軟部組織感染症(SSTI)の感染微生物としては、A郡β溶連菌と黄色ブドウ球菌の2つが重要である。
SSTIの治療に使われる代表的な抗菌薬には、セファレキシン250mg、セファクロル250mg、アモキシシリン250mgがある。(*βラクタム系がアレルギーの場合はクリンダマイシン)
セファレキシンは吸収率が高く、血中濃度を維持しやすい点でも有効であり、カプセル・錠剤・細粒・ドライシロップ等剤形も豊富にそろっている。セファレキシンとセファクロルはどちらも蜂窩織炎の起炎菌をカバーできるが、バイオアベイラビリティや1日の服用回数、剤形の豊富さ、保険最大用量で比べるとセファレキシンに軍配が上がる。処方提案時はこのような比較が役に立つ。
第3世代経口セフェムは、消化管吸収率が低いため求める効果が得られず、広域スペクトルで耐性菌の誘導につながりやすいこともあり、第一選択では使わず温存される。
キノロン系は在宅医療で1日に複数回の服用が難しい場合に選択肢となるが、広域スペクトルのため、汎用すると緑膿菌や腸球菌群に対して必要な時に感受性が低下してしまうリスクがある。さらに、消化器症状、神経症状、アキレス腱炎などの有害事象が多い点や、酸化マグネシウムや鉄剤を服用している高齢者ではキノロン系の作用減弱に注意が必要である。
4.抗菌薬モニタリングを
抗菌薬の効果判定方法として、以下の3ステップがある。
- 投与を開始して48~72時間を目安に、最初の症状と比較して良くなっているか確認(画像で比較できると良い)
- 抗菌薬の選択は妥当か否かを症状の経過から判断、投与経路や投与量は適切かを検討
- 副作用症状の発言はないか、広域の抗菌薬で開始した場合は狭域にスイッチできないかをアセスメントする
CRPや発熱など数値の変化だけで追うのではなく、患者の症状変化を追ってモニタリングすることがポイントとなる。
5.感染症治療の薬歴記載方法
感染症治療の薬歴に記載するのが望ましい内容として、以下の項目が挙げられる。
・想定感染臓器はどこか?
・想定起炎菌は何か?
・十分な投与量か?
・排泄臓器の機能から適切な投与量・投与間隔か?
・投与期間は?
具体的にSOAP薬歴に落とし込むと以下のようになる。
(S)患部・症状の特徴、患者負担になっていること、発熱・随伴症状
(O)抗菌薬指示量・開始日など、身体・検査所見(体重と腎機能は必須)、画像撮影可能であれば添付
(A)想定起炎菌、抗菌薬の妥当性(種類、重症度、腎機能、PK-PDによる投与設計)
(P)EP:抗菌薬服薬指導内容
感染症マネジメントは一人で追うのは難しいため、薬局全体でつなぐ薬歴の意識を持ちながら、みんなでモニタリングして患者を守り、適切な治療が行われるように努めることが重要である。
本項の締めくくりに感染症治療の薬歴記載について解説をいただき、感染症マネジメントでは薬局全体で患者さまを見守ることが重要と述べられていました。
弊社の「MAPsfor PHARMACY 」「MAPsfor PHARMACY DX」シリーズで搭載している電子薬歴システムもまさに薬局内の情報連携をスムーズに実施できるように設計しております。充実した薬物治療を実践するためのシステム提案を行なっておりますので、ぜひ弊社にご相談下さい。
(EM-AVALON編集部より)