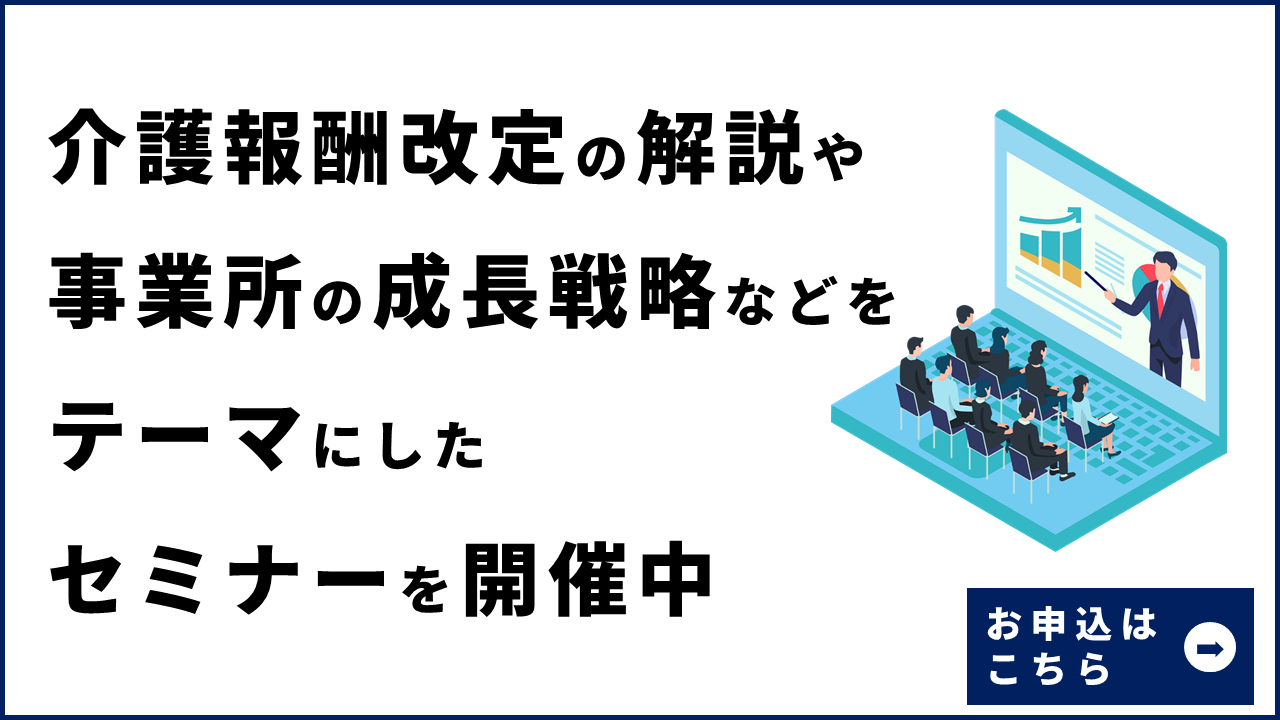- 介護/福祉
- #改定情報
- #施設経営
令和6年度介護報酬改定の読み解きと令和9年度法改正・報酬改定に向けた最新動向
2024.06.24
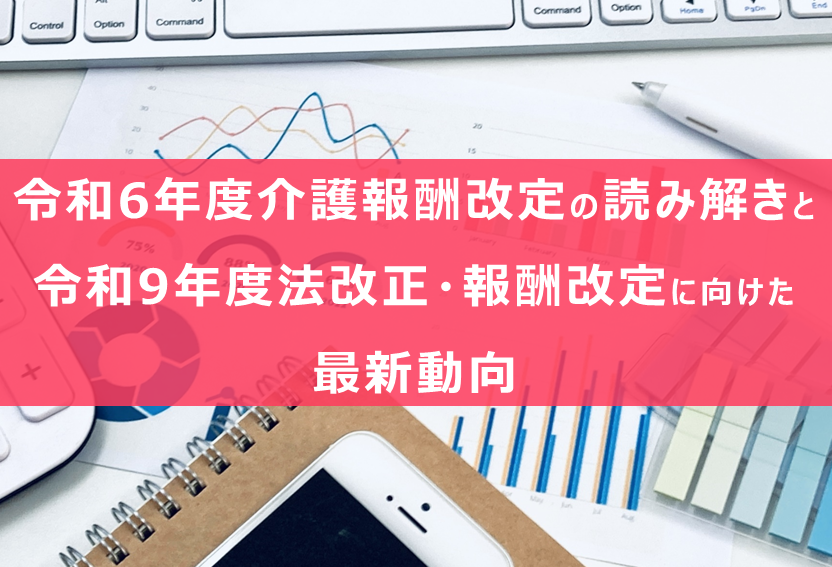
令和6年度介護報酬改定の全体を振り返るとともに、令和9年度の法改正・報酬改定に向けた大変革への読み解きを論考したいと思います。
まず、令和6年度介護報酬改定の全体改定率は1.59%増(うち0.98%は処遇改善、0.61%を事業者へ配分)であり、過去2番目に大きな上げ幅となりました。また、処遇改善加算は1本化されるとともに、単位数も大きく引きあげられ、理論値では、2年分で4.5%の賃上げが可能な予算配分となります。コロナ禍や物価高騰による影響を大きく受けている介護事業者にとっては、決して十分な上げ幅とは言えませんが、全体としては一定の成果と言える水準にあると思います。
しかしながら、直近の経営調査による収支差率が高かった「訪問介護」、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、「夜間対応型訪問介護」の3サービスは、まさかの基本報酬単位のマイナスとなるなど、サービスによる濃淡も大きくなっています。
今回の改定にタイトルをつけるならば、何よりも最優先されたことは職員の処遇改善であり、「賃上げ改定」という表現が適切であると思います。事業者は、1本化された処遇改善加算を確実に算定し、公平かつ適正な評価に基づき、職員への納得感ある分配を行うことが何よりも大切です。同時に、分配方法について職員への説明を丁寧に行う必要があります。
また、今回の改定内容は6年に一度の同時改定でありながら、前回改定ほどの変革インパクトではありません。しかしながら、改革の歩みが減退していると誤った認識をもってはいけません。4つの基本的視点として示された「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立支援・重度化に向けた対応」「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」「制度の安定性・持続可能性の確保」に基づいた見直しが着実に実施されることになります。例えば、LIFEに関連した科学的介護推進体制加算は、点数の拡充、新たなサービス追加はありませんでしたが、入力項目の簡素化や提出時期の統一、フィードバックの充実などが行われる予定であり、新たな試みを行うのではなく、前回改定の課題を整理し、着実に現場での科学的介護の定着を目指す方針であります。
一方で、いくぶん踏み込んだ改革が進められたテーマは「生産性向上」「DX推進」であります。居宅介護支援における逓減制の更なる拡大、施設におけるロボット・ICT機器活用による新加算の創設、特定施設における3対1の人員配置要件の特例緩和など、こちらは現場への変革を迫る強いメッセージともなりました。
今回の改定は、「将来の大変革に向けた土台固めの改定」と位置付けることも出来きます。コロナ禍や欧州での戦争に端を発した物価高騰のような異例ともいえる社会情勢の変化によって大幅なプラス改定となりましたが、将来は大きなプラス改定の実現可能性は低いと言わざるを得ません。長期視点で考えれば報酬削減とともに、大きな制度改革が行われると思います。今回の改定でどうにか確保出来たプラス改定のうちに、大変革に向けた、土台づくりを行うための3年間であると理解し、介護事業者は、運営改革・現場での介護の在り方の変革が不可欠であることを肝に命じなければなりません。
目下は、令和6年度介護報酬改定が施行され、事業者はようやくひと段落ついたばかりのとこでありますが、令和9年度の法改正・報酬改定に向けた動きは早速活発になっています。今後の大注目は、すでに原案が示されていますが、6月21日ごろに閣議決定予定となる「経済財政運営と改革の基本方針2024(骨太方針2024)」の中身です。毎年政府より示される今後の政策の指針となります。この骨太方針に記載された内容は、どのような形に着地するにせよ原則は、実現に向けた政策立案が進められます。骨太方針2024に、社会保障政策がどのような記述となるかは注目です。
その骨太方針2024の取りまとめに向けて、4月16日に財務省は財政審を開催し、社会保障をテーマとした議論を行い、5月21日には「我が国の財政運営の進むべき方向」と題した建議を政府に提出しました。財政再建に向けた社会保障費の抑制政策が中心であり、介護事業者にとっては厳しい提言がいくつも示されています。
また、5月23日に、岸田総理を議長とする「経済財政諮問会議」が開催されました。この会議の議員は、主要閣僚に加えて、財界人が多数の構成となっており、社会保障改革を推進していく立場での議論となります。今回の会議において、岸田総理は、「医療費・介護費の適正化に向けた改革を前進させる」と発言しました。この発言は大変重たい言葉です。政府が適正化と表現した際は、実質的な削減を意味すると捉えても過言ではありません。社会保障は削減すべき予算ではないとの認識から、支出の適正化、無駄をなくすという観点から、実質的には削減を意味します。この総理の発言は、骨太方針2024の中身にも一定の影響を及ぼすことになります。
現在示されている骨太方針2024の原案においては、「医療・介護等の不断の改革により、ワイズスペンディングを徹底し、保険料負担の上昇を抑制することが極めて重要である。」と記されており、「不断の改革」「ワイズスペンディグ」といった文言はあるものの「適正化」等の直接的なマイナス改定を示唆する表現となっていないことには一安心です。しかしながら、「介護保険制度について、利用者負担が2割となる「一定以上所得」の判断基準の見直し、 ケアマネジメントに関する給付の在り方、軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方については、第10期介護保険事業計画期間の開始の前までに検討を行い」「高齢者向け住宅の入居者に対する過剰な介護サービス提供(いわゆる「囲い込み」)の問題…実効性ある対策を講じる。」と記されており、財政再建に向けた具体策の検討方針が示された形となり、令和9年度の法改正・報酬改定の議論にも大きな影響を及ぼすこととなります。
間もなく骨太方針2024が正式に閣議決定されることとなります。そのなかみは大注目すべきです。加えて、厚労省は、ケアマネジメントの在り方に関する検討会を今年度新たに設置し、ケアマネジャーの在り方の見直しを行うこととなります。また、外国人活用における検討会も間もなく、中間報告書を取りまとめる予定となっており、訪問介護における特定技能の解禁の方向性が示されることになります。将来の大きな制度改革に向けた動きがまさに今始まろうとしています。