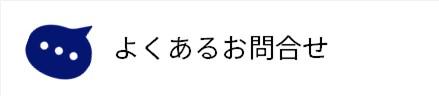- 調剤
- #改定情報
薬価の中間年改定
2024.09.02

7月17日、中央社会保険医療協議会(中医協)薬価専門部会で2025年度の中間年改定に向けた議論が始まった。薬局側は毎年改定による資産の目減りなどの負担を訴え、支払い側は毎年改定の原則を強調している(7月19日付薬事日報)。
薬価の毎年改定に関する議論は、2016年にとりまとめられた「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」で、乖離率の高い品目について毎年薬価を改定することをもとめたことに端を発する。その後、2020年6月17日の中医協薬価専門部会で、2号側や卸団体代表などが「コロナ禍の真っ只中で調査の実施は不可能だ」と口をそろえる中、1号側が「とにかく実施する」一点を死守し、実施しないという結論に至ることを阻止した。続く7月17日に閣議決定された「骨太方針2020」で翌年の薬価改定が盛り込まれ、次の7月22日の薬価専門部会で実施が既定路線となった。つまり、中医協での議論で決まったというよりも閣議決定で決着がついた。この際、「2021年の中間年改定は特例的な扱いなのか?」という確認に対して政府側は明確に回答せず、2023年度に2回目の中間年改定が実施された。
先述のように、薬局や医療機関もメーカーも卸も中間年改定には反対の立場をとっている。たとえば日本薬剤師会の岩月新会長も7月17日の定例記者会見で、薬価の中間年改定について中止や延期、あるいは制度そのものの廃止を求めていくと話している(7月24日PharmacyNewsBreak)。しかし管見では今のところ、2つの理由で中医協での議論の方向性が変わることは期待しにくい。
一つには、医療側が負担を訴えることにどれだけの説得力があるのか?というハードルがある。そもそも、2020年に医療現場や物流が混乱を極めた時期に「現場は大変だ」という訴えがあったにも関わらず「日本中が大変な今だからこそ国民の医療費負担を軽減することが必要だ」というロジックで実施されたという経緯があり、1号側と2号側との間で議論がかみ合わないまま事態が進行している。筆者個人の肌感覚としては、後発品の普及を目的として選定療養制度を本来の趣旨と異なる形で流用するような政府が「国民の医療費の負担を軽減するため」などというロジックを使う点に正直なところ違和感を覚える。しかし、この「国民の負担」という論点を土俵として薬価政策の議論を噛み合わせることが必要で、安定供給にどのような影響が及んでいるのかといった点を実際に調査し、中間年改定のメリットとデメリットとをデータとして示さなければ方向性は変わらないだろう。
二つ目には、乖離率はどこまで下げ続けるべきなのか?という問題がある。医薬品の価格を、(切り下げるという意味ではなく)本来の意味で「適正化」することは当然必要だとしても、画期的な新薬に対しては手厚く薬価を配分し、長期収載品や後発品はどんどん切り下げていくという二極化を目指すこと自体は決して自明ではなく、乖離率に着目して際限なく価格を切り下げ続ける政策の副作用でしかない。「進化系のクロワッサン」は儲けてよいが「昔ながらの製法のメロンパン」はいくら美味しくても利益をあげるべきではない、などという商業倫理はどこにもなく、古い医薬品であっても効果があるのであればそれに見合った価格が維持されるべきだ。製薬会社による医薬品のイノベーションを期待して投資することは大切だが、その原資として乖離率(薬価差)が用いられ、結果的に患者が利用できる医薬品の安定供給に影響が及ぶのであれば、乖離率に注目して薬価を切り下げる手法自体を見直す必要があるのではないだろうか。そもそも社会保障費の支出を抑制しなければならない状況の原因を日本経済の長期的低迷に帰するにせよ少子高齢化に帰するにせよ、その責任を負うべきは国民ではなく政府なのではないだろうか?製薬会社とアカデミアにイノベーションを促す機能は経済産業省や文部科学省が担うべきではないか、といった議論に期待したいのだが、あまり深化できていないような印象を受ける。
薬剤師業界は、中医協の中でも調剤報酬の議論に注目し、政治力を投入しようとしてきたわけだが、むしろ薬価政策のプロセスにこそ資源を投入し介入すべきではないかと筆者は考える。