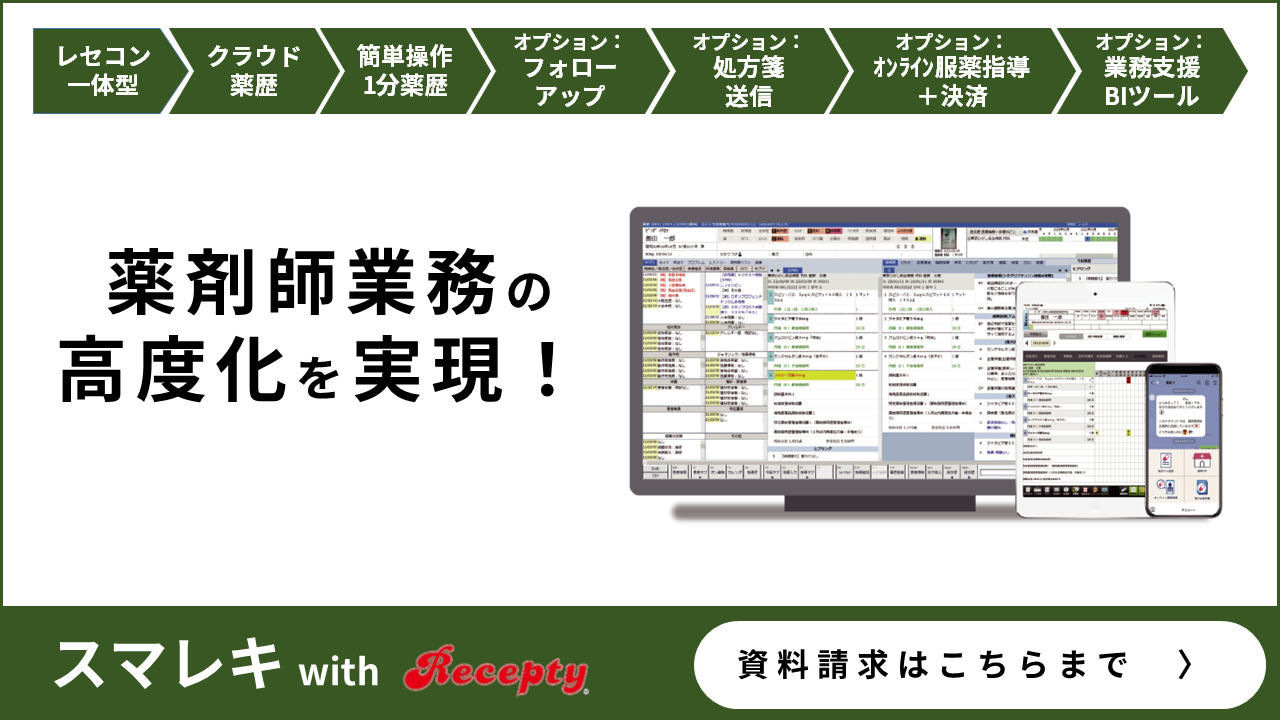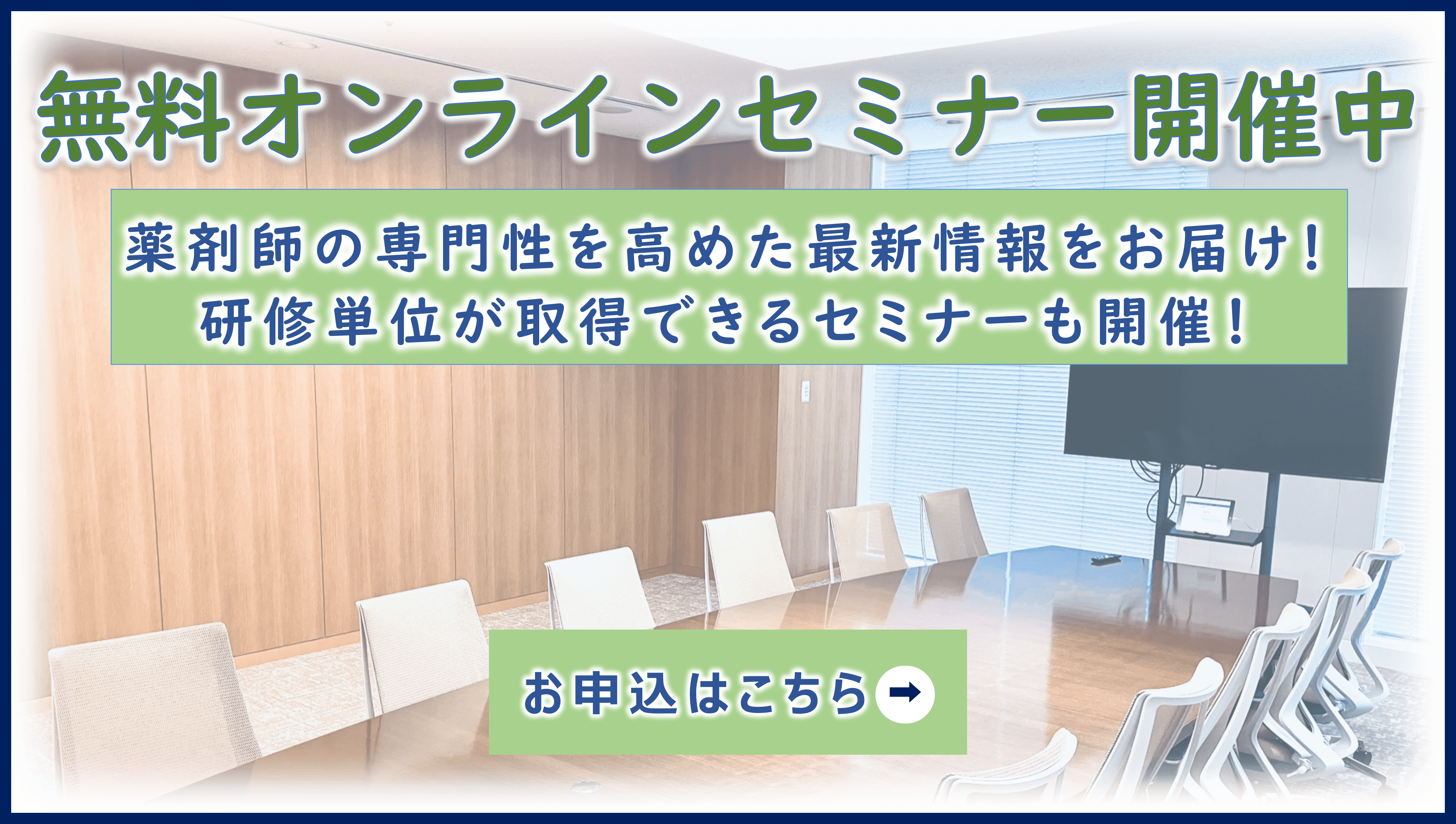- 調剤
- #薬局経営
在宅専門薬局と細分化の是非
2025.03.24

1月31日に厚生労働省で開催された第12回薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会で、複数の委員から「在宅専門クリニックや訪問看護ステーションがあってよいのに在宅専門薬局があってはいけないのはおかしいのでは」という意見があり(「在宅だけ」というよりも「在宅メインで経営が成り立つ」というようなニュアンスだったとのことだ)、これに対して日本薬剤師会は「薬局機能の細分化につながる」として否定的な見解を示したらしい。「在宅医療を利用する期間だけその薬局を使い、通常の通院治療に戻る際には別の薬局に切り替えるというのではかかりつけ機能を持ちえない」という主旨のようだ。
薬を使う側(患者や医療機関)からすれば「必要な薬をすぐに持ってきてもらえるのであればどんな薬局でも関係ない」と考え、一方の薬剤師業界の側は「どんな薬局が持っていくかは自分たちにとって大問題だ」という構図になっている。しかし、個性など皆無の「どんな薬局でも関係ない」調剤サービスを目指して制度を設計しているのは他ならぬ薬局と政府の側であり、保険薬局であれば制度的に一定の品質が担保されていることになっている以上、一見すると矛盾があるように感じられる。
反論の真意としては、薬局の専門化を認めてしまうと、薬局が企業として効率化を追求しすぎた場合に、採算性の高い処方箋だけを応需して在庫や手間の面から採算性の低い処方箋を拒否してしまうようになる(ミクロ経済学や保険業界でいうところの「クリーム・スキミング」)可能性を恐れているのだろう。
経済学的には、クリーム・スキミングは売り手と買い手との間の情報の非対称性によって生じるとされ、その対策として情報の透明化がなされたりするが、保険調剤の場合にはそもそも患者の自由意志による決定権がほとんどないため、薬局の情報をすべてガラス張りにしたとしてもこのクリーム・スキミングはおそらく解決しない(逆に考えれば、患者が自由に決定できる部分を増やすことで解決できるようになる可能性はある)。
薬局の「かかりつけ機能」や「服薬情報の一元管理」といったことが喫緊の要請として制度的に実装されるようになったのは2015年に厚生労働省が「患者のための薬局ビジョン」を公表した頃以来だが、そこから2040年ごろに向けて我が国の多死社会はピークに達し、同時に、医療情報や健診情報はマイナンバーカードに紐づけられ、薬局は「一元管理の主体」ではなく「政府によって一元管理化された情報の窓口」へと役割を変えていく。このような変化の中で、薬局の「患者の服薬情報の一元管理」という機能に重きを置くことは果たして賢明なのだろうか。あるいは、医薬品の供給が不安定な状況は当分続くと想定した上で、それぞれの薬局が品薄な在庫を分譲し続けることが望ましいのだろうか、それよりも患者を紹介するような形で薬局同士が得意分野をカバーしながら連携することはできないのだろうか(もしこれを目指すのであれば、取り組むべき課題は「服薬情報の一元管理」ではなく、「服薬情報の薬局横断的な標準化」となる)。
現在の薬局数が過剰であり、何割かは減っていかざるを得ないと考えた時に、どのような薬局が生き残るべきか?という冷徹な判断を誰かがしなければならない。「判断しない」、つまり自由競争に任せるのも一つの選択だが、今のところは、すべての薬局が小児から在宅まで(刻みの生薬の調剤は無視されがちだが)在庫や設備、労働時間で対応するといった近代五種競技のようなハードな種目で競うことが選択されている。その結果として、もともと体力もありトレーニング環境も揃ったプレイヤー(薬局)に適度に負荷をかけて筋肉質に育て上げ、体力のない小規模薬局、特に面分業で対応しているような薬局を淘汰することを期待しているのであれば、それはそれで一見識ということになるだろう。
ただ、もしもそれが小規模な薬局の生き残りを意図した制度設計なのであれば、在宅のニーズの増加といった環境の変化に対応することすら難しくしてしまうような「薬局の理想像」なるものとその実現への道筋を、一度立ち止まって描き直した方が良いのではないだろうか。