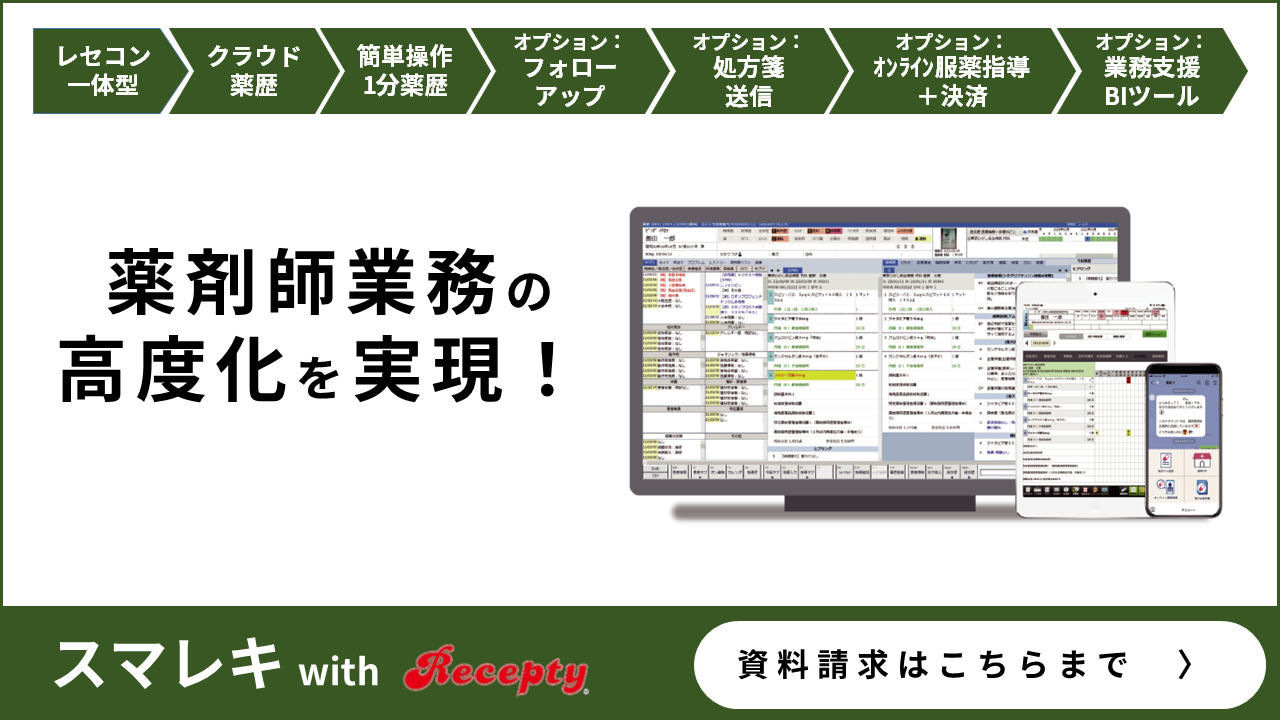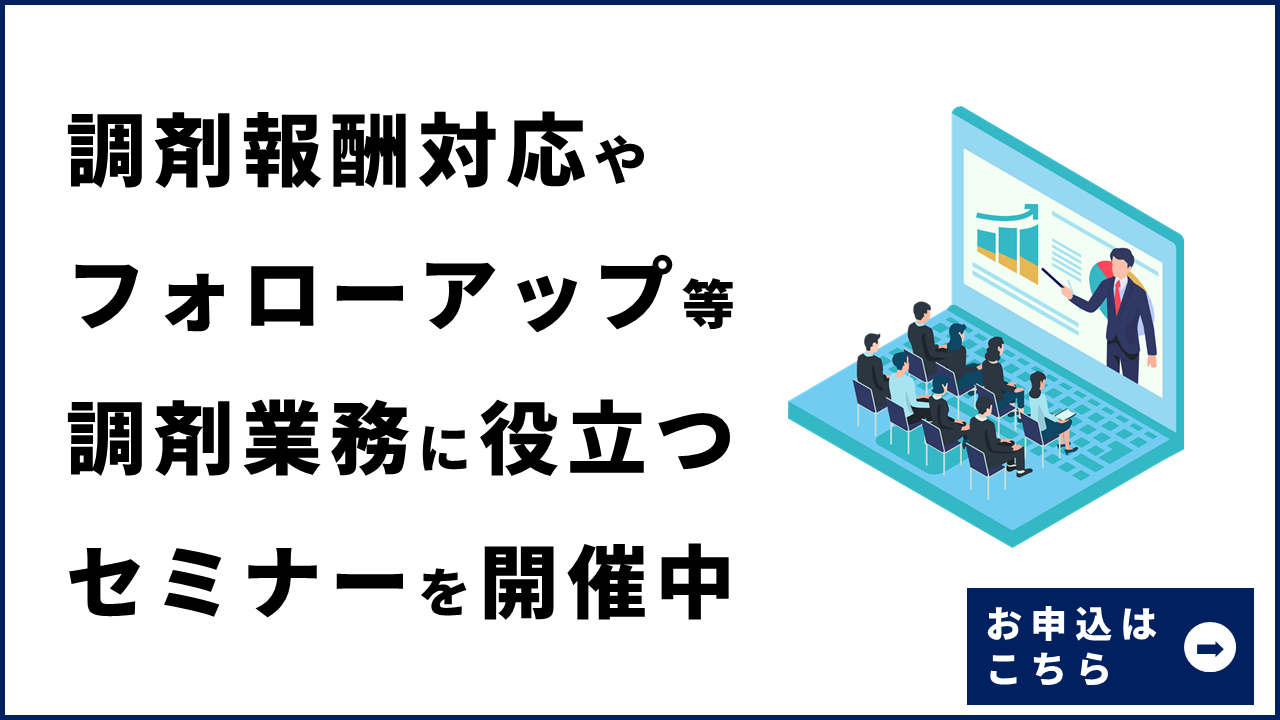- 調剤
- #トレンド
非処方箋医薬品と薬局を巡る議論
2025.04.30
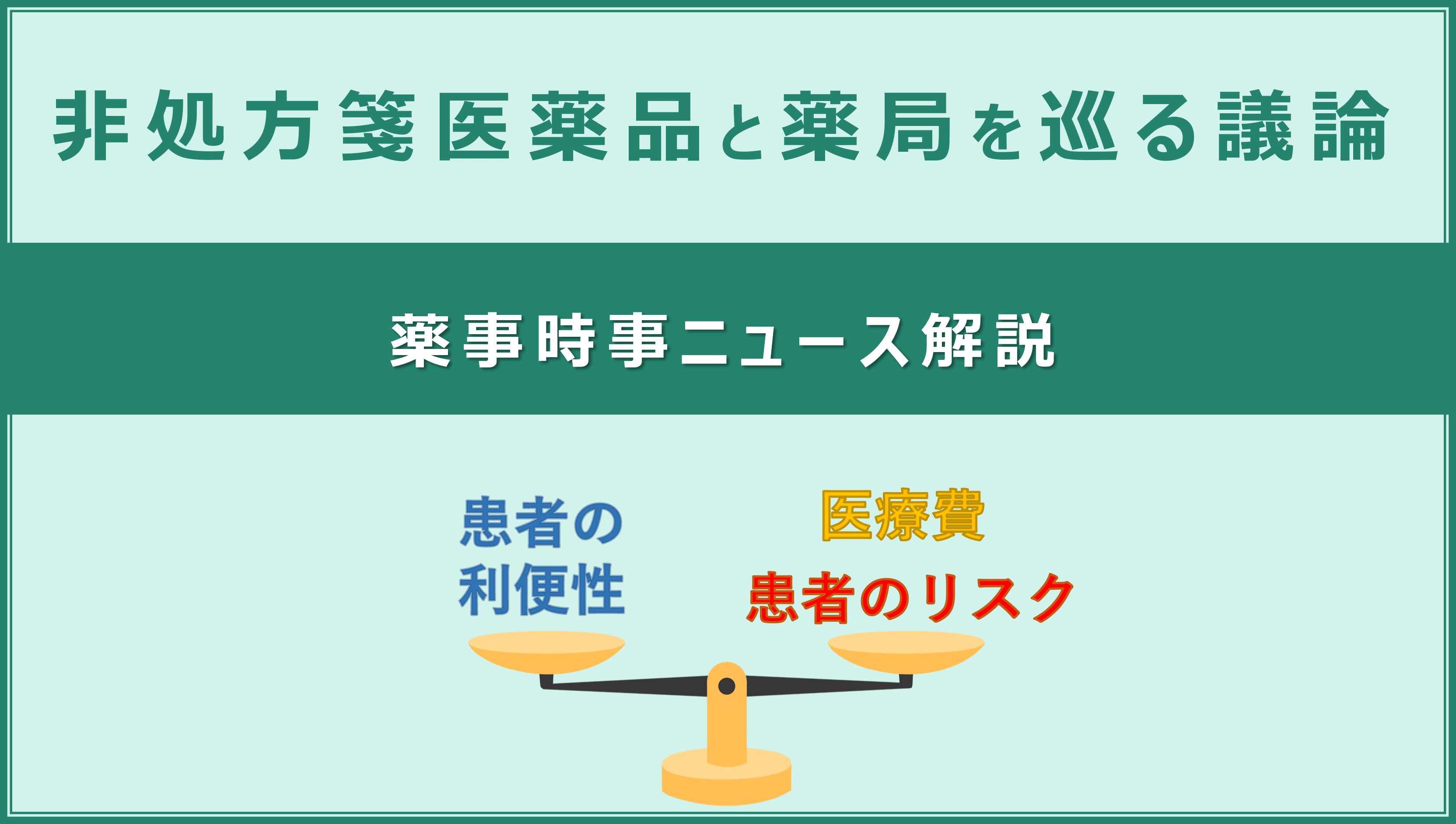
保険診療の保険給付をめぐって、昨年の暮れから短期間で3つの議論が出現した。
(1) 高額療養費制度の上限額の見直し (2024年11月21日 厚生労働省社会保障審議会医療保険部会 *1)
(2) 零売の見直しの提言 (2025年2月5日 日本総研・成瀬道紀氏 *2)
(3) 非医療用医薬品の保険給付の適用除外 (2025年2月3日 日本維新の会・岩谷良平氏 *3)
(1)に関しては、すでに凍結ということで決着しているが、(2)と(3)に関しては現在でも議論がされており、先が見えない。しかも薬局の在り方を大きく変える可能性があるため、早い時点で議論が必要になると思われる論点を3つほど整理しておきたい。
【目次】
1.論点1 そもそもなぜ薬剤料なのか?
「少子高齢化にともなって社会保障費が急増するという問題の中で、薬剤料の負担が大きくなっている」というイメージが自明視されているが、本当にそうなのか?という点は確認しておくべきだろう。
「医科・歯科・調剤医療費の動向調査」を見ると、「電算処理分について」という制約はあるものの過去の医療費と薬剤費の変化を追うことができる。ここでは医科・歯科・調剤のデータが入手可能な2018年度分と最新の2025年度分との増減を比較してみる。
|
|
2018年度(億円) |
2025年度(億円) |
|
|
医療費 |
総医療費 |
406,544 |
421,264 |
|
医科 |
301,712 |
306,590 |
|
|
歯科 |
28,167 |
31,995 |
|
|
調剤 |
76,664 |
82,678 |
|
|
薬剤費 |
総薬剤費 |
94,860 |
96,999 |
|
医科 |
37,246 |
36,748 |
|
|
歯科 |
201 |
209 |
|
|
調剤 |
57,413 |
60,041 |
|
|
増減額 |
総医療費 |
- |
14,720 |
|
薬剤費 |
- |
2,139 |
|
|
増減率 |
総医療費 |
- |
3.62% |
|
薬剤費 |
- |
2.25% |
|
|
総薬剤費/総医療費 |
23.3% |
23.0% |
|
2025年度の医療費全体の規模は42兆円で、この7年間に1.5兆円近く増加しているのだが、その中で薬剤費の増加額は2000億円にすぎず、増加率も医療費全体の増加率(3.62%)より低い(2.25%)(ちなみに、政府の一般会計の歳出の増加率は同じ期間で25.9%)。これは保険薬局が後発品の使用などの努力によって薬剤費を抑えることに成功しているとみるべきだ。薬剤師は薬の専門家として、社会保障費や薬剤費といった領域でも積極的にコミュニケーションをとるべきで、「薬局がここまで頑張っているのに、なぜさらに薬剤費を抑制しなければならないのか」という根拠を示すことを政府に求めた方がよいのではないだろうか。
2.論点2 患者のリスクにどう向き合うか?
零売とは、患者にとっては処方薬を「受診しなくても薬局で直接買える」という利便性が「全額自己負担(そして医師の評価を受けないことによるリスクの増加)」という負担を上回ると判断した場合に選択肢が増えるにすぎない。しかし処方医にとっては患者の選択権増加分だけ自らの処方権が制約を受けるという感覚があるため、特に開業医を中心として「最適な治療の機会を失う危険性」といった反論がみられる。
世界的には「患者の選択権が増えることは患者にとって総合的に不利益になる」という議論はすでに克服されており、「患者の選択権を制限しよう」ではなく「患者の選択権を医療従事者がサポートしよう」という方向が目指されているのではないだろうか。この論点を改めて丁寧に議論することは重要かもしれない。
3.論点3 「薬剤師の職能」は拡大するのか?
保険給付の適用除外については、大きく分ければ
A 医師の処方を残しつつ、選定療養を拡大してOTC類似薬を10割負担とする方法
B医師の処方と関わりなく薬局で直接購入する方法
の2通り考えられ、現時点ではBのタイプが想定されているようだ。この際に問題となるのは、「近隣に薬局がないから院内処方にせざるをえない」という医療機関にかかっている患者は非処方箋医薬品をどのように入手すればよいのか?という問題で、最も自然な答えは「医療機関が自費で販売すればよい」となる。そうなれば「やむを得ない場合に限り医療機関が自らOTCを販売する」という例外規定を最大限に拡大解釈する新型の院内処方が始まり、短期間のうちに薬剤師の職能を狭めることになると筆者は想像する。
逆に零売の場合には、今までは販売できなかった医薬品を販売できるようになるため、薬剤師にとっては職能の範囲は(一時的にせよ)拡大する。
4.まとめ
零売については、今まではグレーだったものを黒とした(いわゆる「ルールを明確化しただけ」)直後なだけに、白く塗り直すという軌道修正は政府の「無謬性」の壁を考えると当面は実現が難しいだろう。むしろ保険給付の適用除外の方が議論しやすいはずだが、政策単独の評価よりも政局がらみのトレードオフによって決着する展開になるかもしれない。
今回の制度改革をどう考えるべきか?という点について、さまざまな利害関係が錯綜しているために立ち位置の定め方が難しいが、個人的には、将来的に「親が経済的な負担を理由に子供の治療をためらう」というような事態が生じるようであれば、明確な失敗と断言してよいのではないかと考える。
*1
厚生労働省社会保障審議会(医療保険部会) 第186回 2024年11月21日の議事録
*2
日本総研 ビューポイント No.2024-038
医薬品「零売」規制の妥当性を問う
*3
第217回国会 衆議院 予算委員会 第3号 令和7年2月3日