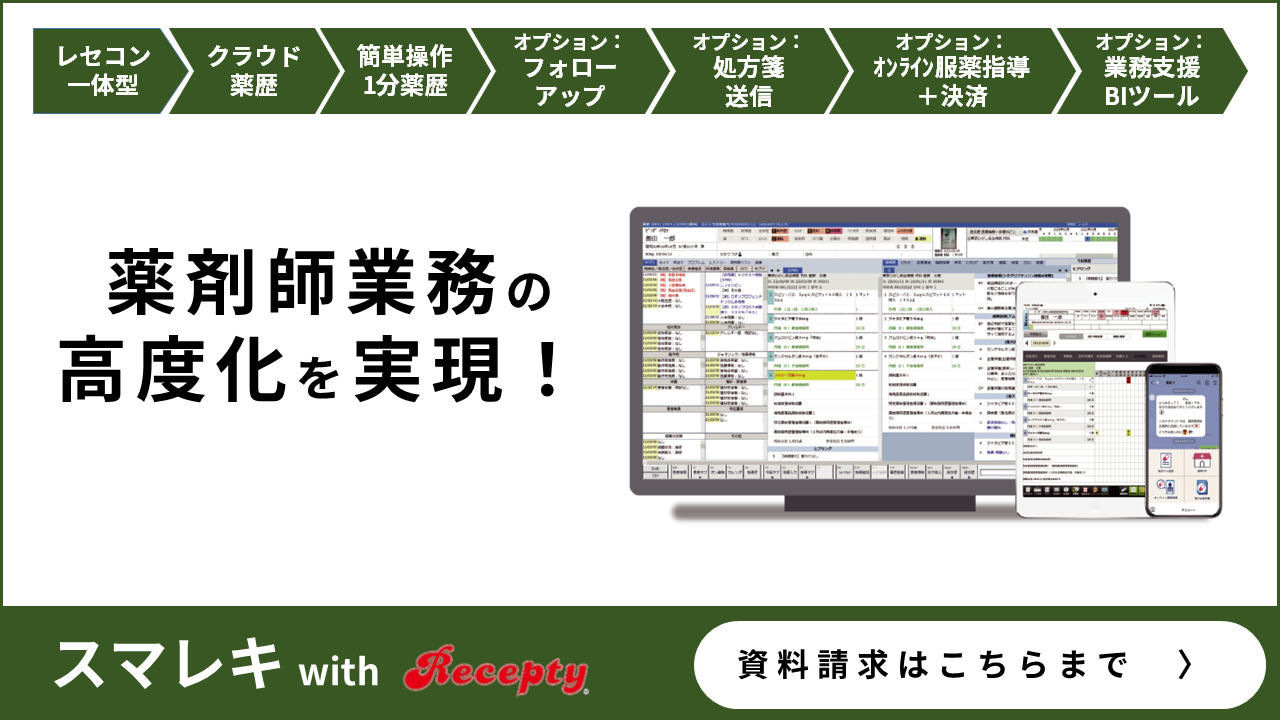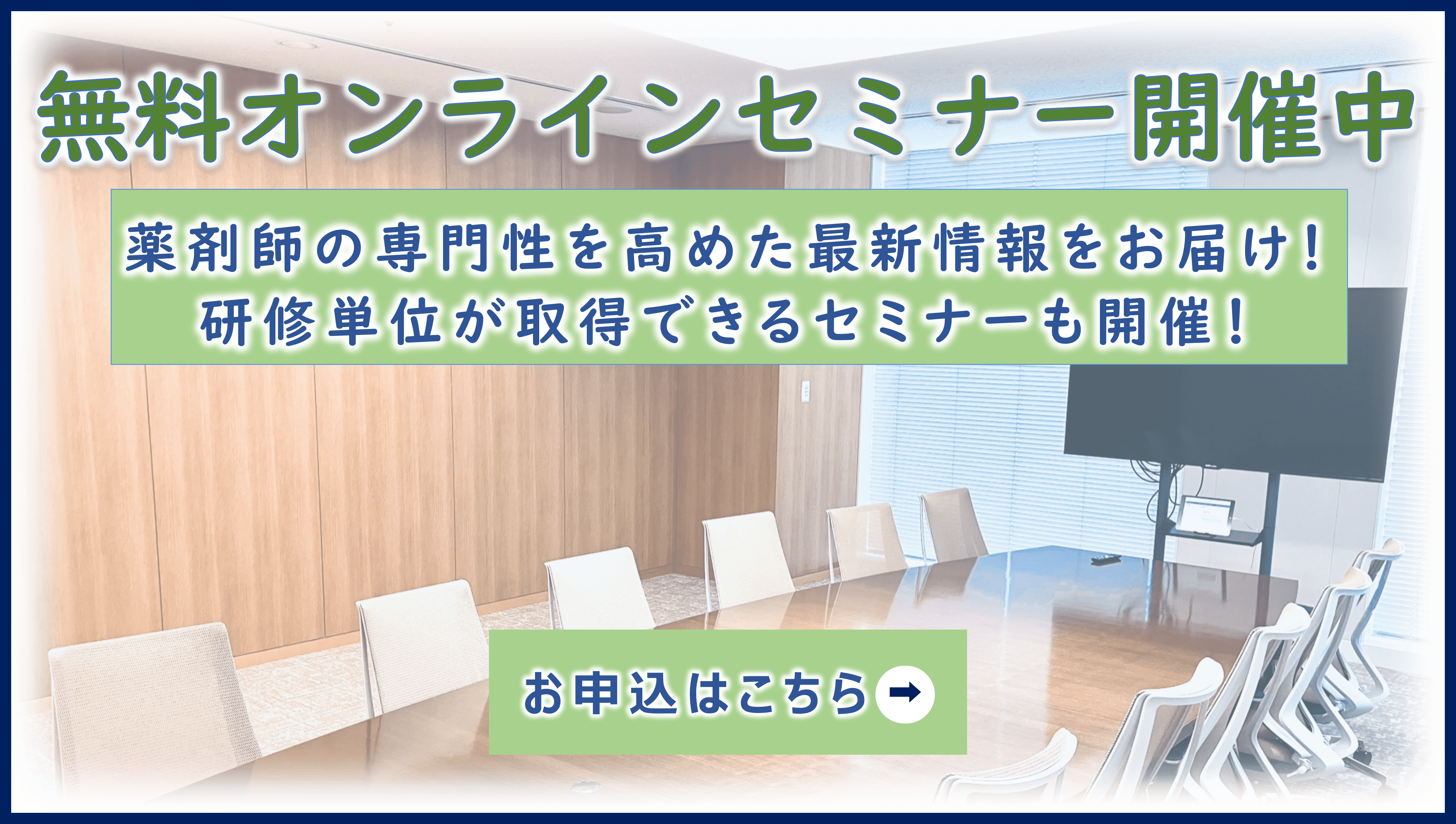- 調剤
- #薬局経営
セミナーレポート「信頼される薬剤師に必要なホスピタリティと傾聴力」
2025.05.21
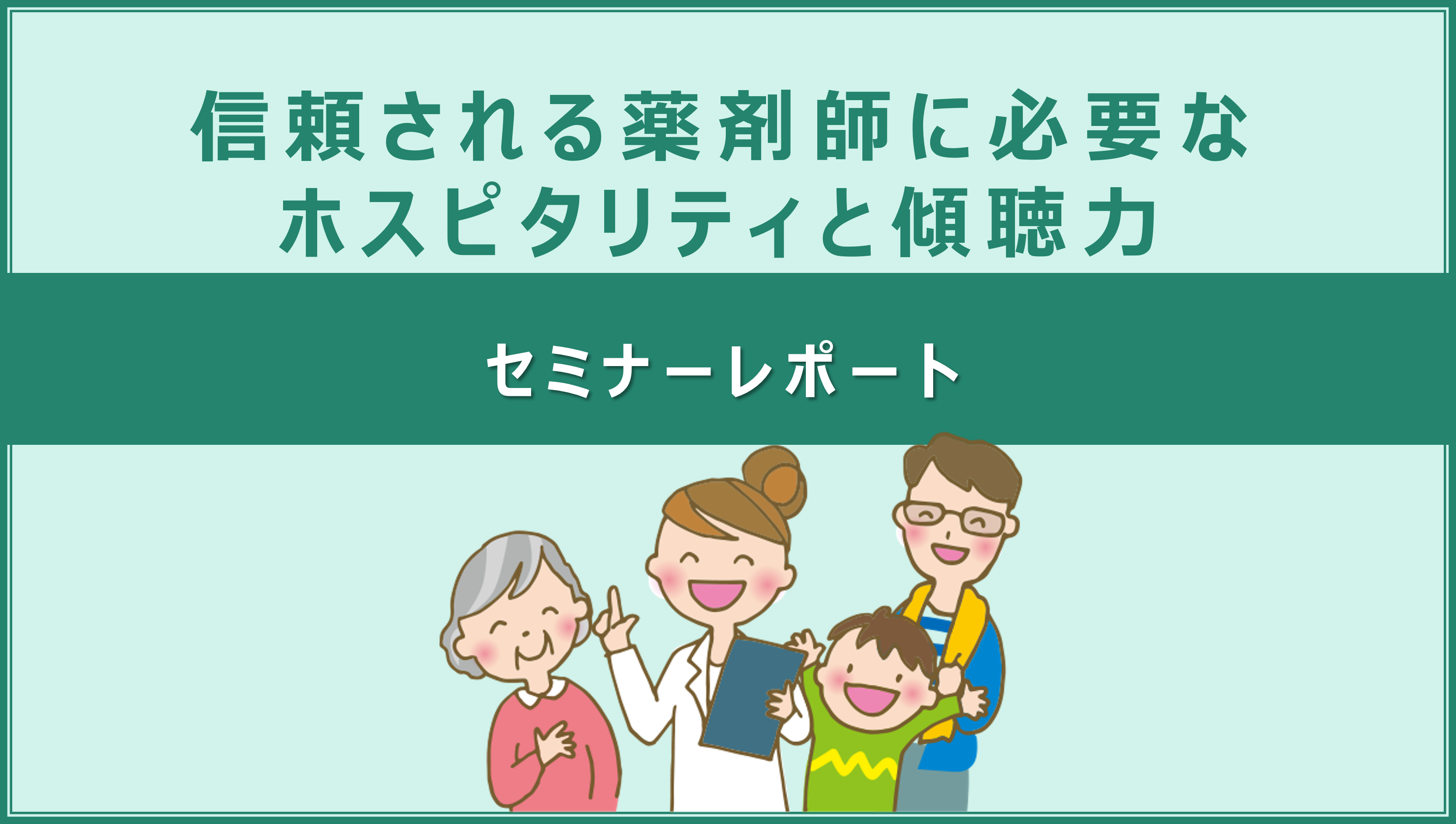
4月27日に一般社団法人ファルマ・プラス主催によるオンラインセミナー「信頼される薬剤師に必要なホスピタリティと傾聴力」が開催された。薬局業務で役立つ具体的な方法を中心に、セミナー内容の一部を紹介する。
【セミナー講師と演題】
演題:信頼される薬剤師に必要なホスピタリティと傾聴力
講師:シュクリア代表(JHMA認定ホスピタリティコーディネーター/薬剤師) 坪田 のり子氏
【目次】
1.薬局におけるホスピタリティとは
薬剤師の役割は「薬物療法の質を向上させること」であり、患者さんとの関わりの中で役割を果たすためにはホスピタリティと傾聴力がポイントとなる。
また、人口減少に伴う患者数の減少や異業種の参入など、薬局は新規の患者さんを獲得するのが難しい状況にある。だからこそ、一度訪れた患者さんに繰り返し来局してもらうことが非常に重要であり、そのためには患者さんの満足度を高めて選ばれる薬局になる必要がある。
一般的に患者さんが薬局に期待するのは「正しい薬がほしい」「できるだけ早く薬がほしい」ということであり、これらが達成された時「患者さんの期待=現実」の状態となる。患者さんの満足度を高めるためには「期待<<現実」の状態を作り出す必要があり、その手段の1つがホスピタリティの提供だ。
薬局におけるホスピタリティとは、ホスピタリティを提供される患者さんと提供する薬剤師がお互いに満足して対等な関係を築き、それによって信頼関係を強め、薬局という空間の価値を高めていくことを指す。ホスピタリティを発揮する考え方を知って、考え方に沿って行動することで、人手が足りず忙しい状況でも自然とホスピタリティが提供できるようになり、満足が広がっていく。
2.ホスピタリティの具体的な手法
ホスピタリティはスキルの1つであり、「観察⇨推理⇨理解⇨行動」という流れがある。
例として、雨の日に来局された患者さんが濡れた傘を持って入口で辺りを見回している状況では、以下のような流れになる。
・濡れた傘を持っている患者さんがいるな(観察)
・傘袋を入れる袋を探しているのかな(推理⇨理解)
・「〇〇さんこんにちは。傘袋をお探しでしょうか?」(行動)
決められたマニュアルに沿った行動だけではなく、一人の患者さんを見て考えて理解して行動するのがホスピタリティである。
服薬指導時のホスピタリティとしては、以下のような丁寧なふるまいを意識することがポイントだ。
- 動作の最後をゆっくりと静かに(おじぎはスッと下げて、ゆっくりと上げる)
- アイコンタクト(忙しい時でもいったん顔を上げて挨拶する)
- 指をそろえる(指を広げるとフレンドリーさが伝わるため、医療機関ではそろえることが推奨される)
3.服薬指導時に大切な積極的傾聴(アクティブリスニング)
日本語の「きく」にはいくつか種類があるが、服薬指導時に重要なのは「聴く」(注意深く意識を向けて耳を傾ける)こと。
健康が失われて喪失感を抱きながら来局されている患者さんに対して、薬剤師が積極的傾聴(アクティブリスニング)を行うことがポイントで、アクティブリスニングでは以下の2点が求められる。
- 患者さんから得た情報を整理する
- 聴こうとする熱意を表現する(うなずき、相槌など)
アクティブリスニングにより、患者さんは喪失感を語れるようになり、薬剤師は苦悩やニーズを感じ取り、生活や気持ちに配慮した服薬指導および適切な薬物療法につながっていく。
4.質問力とナラティブコミュニケーション
傾聴力に加えて質問力も大切である。質問には相手が自由に答えられるオープンクエスチョンと、「はい/いいえ」もしくは短い答えで回答できるクローズドクエスチョンがあるが、
一般的にまずはクローズドクエスチョンで話しやすい環境をつくることがすすめられる。服薬指導も同様で、薬剤師の「この薬を飲んでいてふらつきなどはありませんか?」のような患者さんにあわせた答えやすい質問により、スムーズな服薬指導につながる。
患者さんとの対話の中で薬剤師は「自分の話をしたくなる癖」「意見したくなる癖」など心の癖が出てしまったり、無意識のうちに自分のフィルターを通して患者さんの話を聞いてしまい、捉え方や解釈に偏りが生じてしまったりする点に注意が必要だ。事実に目を向けて、自分の考え方を絶対視せず、柔軟に軌道修正することを意識したい。
さらに、患者さんの訴えの背景にある経験や感情、価値観といった物語を共有するナラティブコミュニケーションが行えると、一人の人としてコミュニケーションが取れるようになり、より患者さんに寄り添った適切なサポートが可能となる。
セミナー主催:一般社団法人ファルマ・プラス